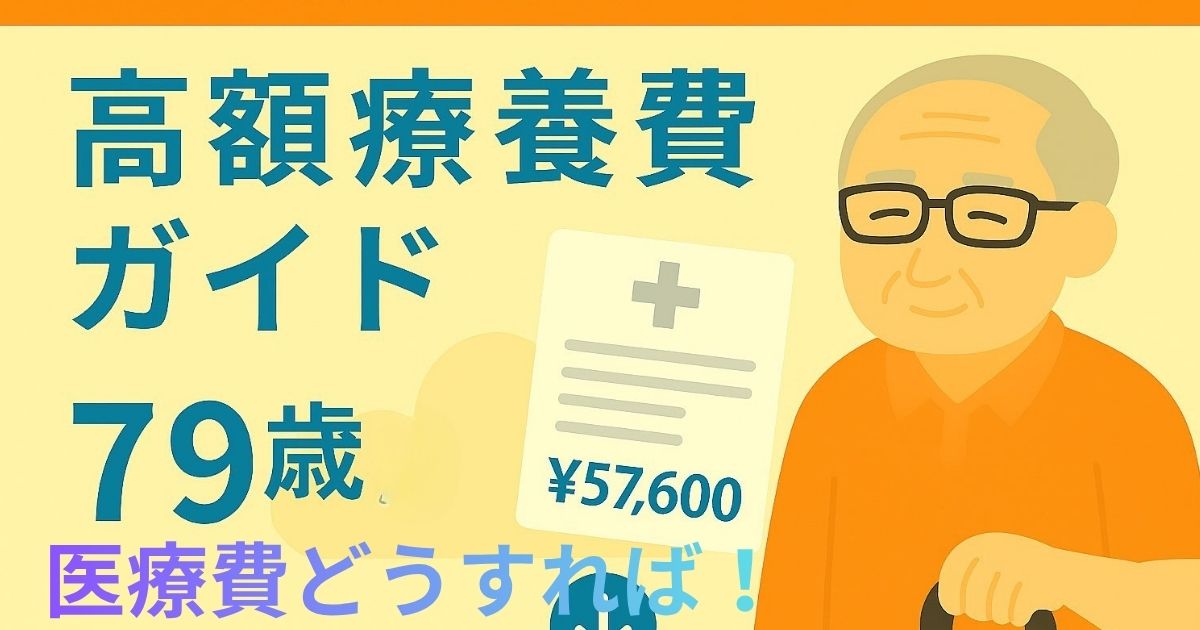75歳からの安心ガイド|後期高齢者の高額療養費制度を【所得区分別】に完全解説

高額療養費制度は、制度の仕組みや所得区分によって自己負担額が変わるため、たしかに複雑に感じやすいですね。
この制度は、「医療費が高額になっても、所得に応じた上限額を超えて払わなくていい」という、後期高齢者の生活を守るための大変重要な仕組みです。
後期高齢者医療制度(原則75歳以上)に特化し、制度の基本から、ご自身の負担上限額、申請方法まで、分かりやすく解説します。
1. 制度の基本と「ここがポイント!」
🔑 ポイント1:保険適用外の費用は対象外
高額療養費制度の対象となるのは、保険診療の対象となる医療費(10割分)の自己負担額のみです。
| 対象外となる主な費用 | 補足説明 |
|---|---|
| 入院時の食費・居住費(差額ベッド代) | 食事代は「食事療養標準負担額」、居住費は保険適用外です。 |
| 保険適用外の治療費 | 先進医療の技術料、自由診療など。 |
| 文書料、雑費 |
🔑 ポイント2:薬代の扱い
薬代は、処方せんによる院外薬局での支払い分も、医療機関での費用と合算して計算されます。ご安心ください。
🔑 ポイント3:計算期間と申請
| 計算期間 | 月の初日から末日までの1ヶ月です。 |
|---|---|
| 申請 | 原則として、最初の1回を申請すれば、次回以降は自動で支給されるケースが多いです。(お住まいの広域連合により異なります) |
| 支給時期 | 通常3~4ヶ月かかります。医療機関からの明細書の審査を経るためです。 |
2. 【最重要】自己負担限度額(月額)の仕組み
自己負担限度額は、後期高齢者医療制度に加入している方の「所得区分」と「窓口負担割合」によって決まります。まずはご自身の区分を確認しましょう。
区分別:自己負担限度額(2024年4月時点)
| 所得区分 | 窓口負担割合 | 外来(個人単位)の上限 | 外来+入院(世帯単位)の上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得Ⅲ | 3割 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) |
外来と同じ |
| 現役並み所得Ⅱ | 3割 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) |
外来と同じ |
| 現役並み所得Ⅰ | 3割 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) |
外来と同じ |
| 一般 | 1割または2割 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (多数回該当:44,400円) |
| 低所得Ⅱ | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
※ 多数回該当とは、直近12ヶ月間に世帯の限度額を超えた月が4回以上あった場合の4回目以降の限度額で、さらに負担が軽減されます。
※ 2割負担となった方には、施行後3年間、1ヶ月の外来負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。
3. 計算と合算のステップ(75歳以上)
75歳以上の方の高額療養費の計算は、「まず個人で外来を計算し、次に世帯で入院と合算する」という2段階で行われます。
ステップ1:外来(通院)の合算・上限適用(個人単位)
まず、個人単位で、その月の外来でかかった医療費(病院、診療所、薬局など全て)を合算し、個人の外来限度額を超えた分を支給します。
- 合算対象:病院、診療所、調剤薬局、訪問看護など。金額に関わらず全て合算できます。
ステップ2:外来+入院の合算・上限適用(世帯単位)
次に、ステップ1で計算後の外来の自己負担額(上限額まで)と、入院の自己負担額を合算し、世帯単位の限度額を超えた分を支給します。
- 世帯合算対象:同じ後期高齢者医療制度に加入している方全員(世帯)の医療費を合算できます。
4. さらなる負担軽減のための制度
4-1. 限度額適用認定証
現役並み所得I・II、低所得I・IIの方は、事前に広域連合に申請して「限度額適用認定証」の交付を受け、窓口で提示することで、医療機関の窓口での支払いを最初から自己負担限度額までに抑えることができます。
※ 一般区分と現役並み所得Ⅲの方は、保険証だけで限度額が適用されるため、原則、申請は不要です。
4-2. 高額介護合算療養費
医療保険と介護保険の両方を利用している世帯が対象です。1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計が所得に応じた年間合算限度額を超えた場合に、その超えた分が支給されます。
4-3. 外来年間合算
一般区分と低所得区分の方は、前年8月1日から7月31日までの1年間の外来自己負担額を合算し、上限額(144,000円)を超えた分が支給されます。長期にわたる通院治療がある方は特に重要です。
5. 【チェックリスト】高額療養費で「損しない」ために
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所得区分の確認 | 毎年届く「後期高齢者医療被保険者証」で、ご自身の所得区分と負担割合を必ず確認しましょう。 |
| 認定証の申請 | 現役並みⅠ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱの方は、入院や高額な外来治療の前に、必ず事前に認定証を申請しましょう。 |
| 世帯合算の確認 | 同じ世帯に加入者がいる場合、世帯合算の通知を見落とさず、申請しましょう。 |
| 2年間の時効 | 支給申請には、診療を受けた月の翌月1日から2年間という時効があります。通知が来ない場合は窓口に相談を。 |
現在79歳の男性、一人暮らしです、仕事は元公務員で
年金が20数万ありますが!?

79歳・一人暮らし・年金20数万円の医療費負担
入退院を繰り返すご友人の医療費負担について、後期高齢者医療制度に基づきわかりやすくまとめました。
1. 窓口での自己負担割合
79歳は後期高齢者医療制度(75歳以上)の対象です。自己負担割合は前年所得で決まります。
お友人の場合:おそらく「2割負担」
- 年金収入:月20数万円 → 年間約240~300万円
- 課税所得28万円超 かつ 合計所得200万円超 → 2割負担に該当
- 元公務員(共済年金)でも負担割合は同じ
| 負担割合 | 条件(単身世帯) |
|---|---|
| 1割 | 年金収入200万円未満 |
| 2割 | 年金収入200万円以上(お友人のケース) |
| 3割 | 課税所得145万円以上(年収383万円相当) |
2. 高額療養費制度(月々の上限あり)
医療費が高額になっても、月57,600円が上限(一般所得者)です。
| 区分 | 月額上限 | 備考 |
|---|---|---|
| 一般所得者(お友人の場合) | 57,600円 | 外来+入院の合計 |
| 外来のみ | 18,000円 | 年間上限144,000円 |
3. その他の負担と支援
入院時の自己負担
- 食事代:1食460円~(低所得者は減額可)
- 差額ベッド代:希望しない限り不要
一人暮らしの支援
- 市区町村の福祉課で見守りサービス相談
- 訪問看護・介護保険の活用
- 生活保護(医療扶助)は年金20数万円では難しい
確認・相談先
- 市区町村 後期高齢者医療窓口:負担割合通知を確認
- ひまわりホットライン:0570-064-091(厚生労働省)
お友人のご健康を心よりお祈りいたします。