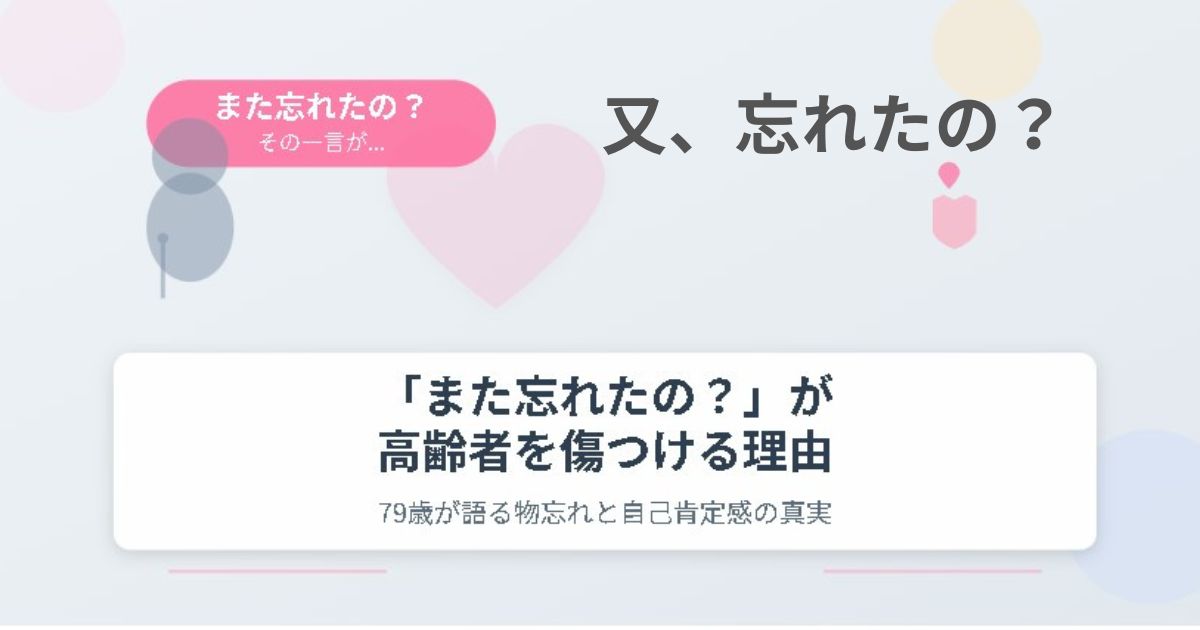はじめに「また忘れたの?」
この一言が、高齢者をどれほど傷つけるか。
79歳の私も、物忘れが増えてきました。
薬を飲み忘れたり、約束を忘れたり。
今日は、物忘れ・認知症への不安と自己肯定感の関係について、
当事者の視点でお話しします。
物忘れへの恐怖
私自身の経験
最近の物忘れ:
薬を飲んだか忘れる
人の名前が出てこない
昨日の夕食が思い出せない
約束の日時を間違える
心の中の声:
「認知症の始まりでは?」
「どんどん悪くなるのでは?」
「家族に迷惑をかける」
物忘れが自己肯定感を下げる理由
①能力の低下を実感
「昔の自分」との比較
②周囲の反応への恐怖
「また忘れたの?」と言われる
③将来への不安
認知症への恐怖
④自己価値の喪失
「もう何もできない」という思い込み
リハビリ仲間の本音
83歳の中村さん(仮名)の話
軽度認知障害(MCI)と診断されました。
娘の反応:
「お父さん、また忘れてる!しっかりして!」
中村さんの気持ち:
「分かっている。忘れたくて忘れているんじゃない」
「自分が一番悔しい」
「娘に責められると、もっと落ち込む」
結果:
自信喪失
家族との会話を避ける
さらに記憶力低下
悪循環
78歳の吉田さん(仮名)の話
物忘れを家族に隠すようになりました。
理由:
「心配かけたくない」
「責められたくない」
「認知症と思われたくない」
隠した結果:
適切な対応が遅れる
孤独感が増す
不安が大きくなる
自己肯定感がさらに低下
「また忘れたの?」の破壊力なぜこの言葉が傷つくのか
①責める口調
「あなたが悪い」というメッセージ
②繰り返しの強調
「また」= 何度も同じ失敗をしている
③能力の否定
「できない人」というレッテル
④追い詰める効果
逃げ場がない
言われた時の高齢者の心理
表面:
「ごめん」と謝る
本心:
情けない
申し訳ない
自分は駄目な人間だ
生きている価値がない
私が言われた経験
薬を飲み忘れた時、「また忘れたの?しっかりしてよ!」
と言われました。
その時の気持ち:
深く傷ついた
自分でも情けないと思っていた
でも責められると、さらに落ち込む
「もう何もできない」と思った
認知症への不安が自己肯定感を下げる
「認知症になったら終わり」という恐怖
多くの高齢者が抱く不安:
自分が自分でなくなる
家族に迷惑をかける
施設に入れられる
人間としての尊厳を失う
この不安が:
日常的なストレス
自己肯定感の低下
生きる意欲の喪失
かえって認知機能低下
「認知症=終わり」ではない
現代の認知症ケア:
早期発見・早期対応
適切な治療で進行を遅らせられる
認知症でも尊厳ある生活
家族や社会のサポート体制
でも、この情報が高齢者に届いていない。
家族ができる適切な対応
①責めない、共に対策を考える
NGな対応:
「また忘れたの?」
「しっかりして!」
「何回言ったら分かるの?」
OKな対応:
「忘れちゃったんだね。一緒に対策を考えよう」
「メモを活用してみる?」
「私もよく忘れるよ。お互い気をつけようね」
②正常な老化と認知症の区別
正常な加齢による物忘れ:
ヒントがあれば思い出せる
日常生活に大きな支障なし
物忘れを自覚している
認知症の可能性:
ヒントがあっても思い出せない
日常生活に支障
物忘れを自覚していない
焦らず、適切に判断:
心配な場合は、早めに専門医へ。
③記憶を補助する工夫を一緒に
具体的な工夫:
カレンダー活用:
大きな字
見やすい場所
約束を書く
メモの活用:
冷蔵庫に貼る
トイレに貼る
目につく場所に
スマホのリマインダー:
薬の時間
約束の時間
定期検診
ルーティン化:
同じ時間に同じこと
習慣化で記憶負担減
私が実践していること:
薬は朝食後、必ず飲む(ルーティン化)
スマホのアラームを活用
妻と毎日予定を確認
メモを常に持ち歩く
④「できること」に注目する
NGな視点:
「できないこと」ばかり見る
OKな視点:
「まだできること」を見つける
例:
料理の味付けは完璧
昔の記憶は鮮明
人の顔は覚えている
趣味の技術は健在
「できること」を認めることで、自己肯定感を保ちます。
⑤本人の気持ちを聞く
問いかけ:
「物忘れが増えて、不安じゃない?」
「心配なこと、話してくれる?」
「一緒に病院に行ってみる?」
傾聴:
否定しない
遮らない
共感する
一緒に考える
認知症予防と新しい挑戦
脳の活性化には新しい刺激
なぜ新しいことが重要か:
脳の神経回路を活性化
認知機能の維持
生きがいの創出
社会とのつながり
私の実践:AIとブログ
79歳からの新しい挑戦:
AI学習
ブログ運営
読者との交流
情報収集と発信
効果:
毎日脳を使う
目標ができる
社会とつながる
生きがいを感じる
認知症予防にもなる
リハビリ仲間の例
80歳で楽器を始めた人:
音楽は脳の多くの領域を活性化
75歳で外国語学習を始めた人:
新しい言語は認知症予防に効果的
82歳でボランティアを始めた人:
社会参加が脳を活性化
記憶より感情を大切に
認知機能が低下しても残るもの
記憶は失われても:
感情は残る
愛情は分かる
雰囲気を感じる
優しさに反応する
家族が大切にすべきこと
「覚えているか」より「感じているか」:
❌「昨日のこと、覚えてる?」(記憶の確認)
✅「一緒にいて、楽しいね」(感情の共有)
❌「私のこと、分かる?」(認識の確認)
✅「大好きだよ」(愛情の表現)
リハビリ施設での光景
認知症が進んだ方でも:
孫の写真を見ると笑顔
好きな音楽で体を揺らす
優しい声かけに反応
手を握ると安心する表情
感情は最後まで残ります。
私が妻に頼んでいること
もし私が認知症になったら
お願いしていること:
責めないでほしい
一緒に笑ってほしい
手を握ってほしい
「愛している」と言ってほしい
妻の返事:
「何があっても、あなたはあなた。ずっと一緒にいるから」
この言葉が、認知症への不安を和らげてくれます。
早期発見・早期対応の重要性
気づいたら、早めに相談
相談先:
かかりつけ医
もの忘れ外来
地域包括支援センター
認知症疾患医療センター
京都市の場合:
認知症初期集中支援チーム
認知症カフェ
家族支援プログラム
早期発見のメリット:
適切な治療で進行を遅らせられる
本人の意思を尊重した計画
家族の準備期間
社会資源の活用
まとめ:物忘れへの適切な対応
責めない
共に対策を考える
できることに注目
本人の気持ちを聞く
早期発見・早期対応
認知症予防:
新しいことへの挑戦
社会とのつながり
脳の活性化
生きがいの創出
家族が大切にすべきこと:
記憶より感情
愛情の表現
尊厳の維持
寄り添う姿勢
79歳からのメッセージ:
物忘れは誰にでも起こります。責める言葉ではなく、一緒に
対策を考える姿勢が、高齢者の自己肯定感を守ります。
次回は「孫が祖父母の自己肯定感を高める効果」を
お伝えしたいと思います。
公式サイトはこちらから:https://nayami-kaisyou.net/