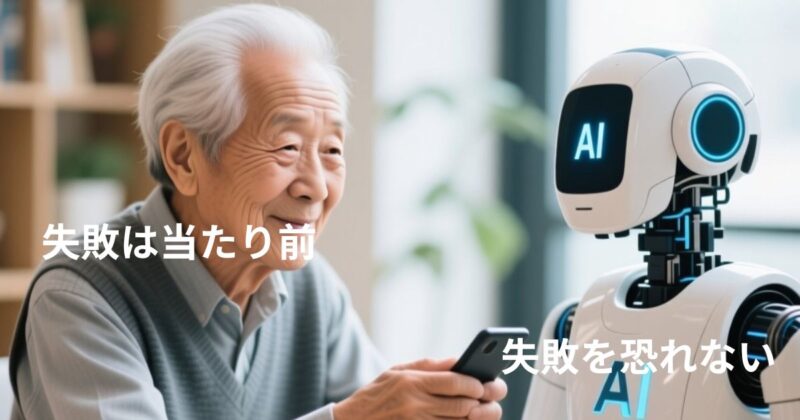
「もう歳なんだから、無理しないで」
新しいことに挑戦しようとした時、この言葉で
止められた経験はありませんか。
79歳の私がAIを学び、ブログを始められたのは、「失敗してもいい」
と言ってくれる環境があったからです。
今日は、高齢者の挑戦と失敗の権利について、実体験をお話しします。
昨年までの私:
悶々とした日々
何もできない無力感
心臓病身体障害者1種1級という制約。
79歳という年齢。
心の声:
「もう何もできない」
「新しいことなんて無理」
「残りの人生、ただ過ごすだけ」
この思考が、自己肯定感をどんどん下げていきました。
挑戦する気力の喪失
考えたこと:
スマホをもっと使いこなしたい → でも難しそう
ブログを書きたい → でも79歳で?
新しい趣味を始めたい → でも今から?
結論:
「やっぱり無理」と諦める日々。
悪循環
挑戦しない
↓
新しい刺激がない
↓
生活が単調
↓
自己肯定感が下がる
↓
さらに挑戦する気力が失われる
妻の一言が変えた
「失敗してもいいじゃない」
AIを学びたいと言った時、妻が言いました:
「失敗してもいいじゃない。やってみることが大事。
私も一緒に学ぶから」
この言葉が:
失敗への恐怖を和らげた
一人じゃないという安心感
挑戦する勇気をくれた
なぜ妻の言葉が効果的だったのか
①失敗を肯定
「失敗してもいい」= 失敗は悪いことではない
②プレッシャーの排除
「成功しなければ」という重圧がない
③伴走の約束
「一緒に」= 孤独ではない
④行動への背中押し
「やってみる」ことの価値を認めてくれた
高齢者が挑戦を諦める理由
①失敗への過度な恐怖
若い時との違い:
若い時:失敗してもやり直せる
高齢者:「最後のチャンス」という重圧
結果:
失敗できないから、挑戦しない。
②周囲の過保護
家族の心配:
「無理しないで」
「危ないから止めなさい」
「できるわけない」
善意が生む悪影響:
能力を信じてもらえないメッセージ
③プライドの問題
高齢者の心理:
「今更、初心者のようなことはできない」
「分からないことを聞くのは恥ずかしい」
「若い人に笑われるのでは」
④過去の成功体験との比較
若い頃の自分:
バリバリ働いていた
何でもできた
尊敬されていた
今の自分:
できないことが増えた
人に聞かないと分からない
役立たず
この比較が、挑戦を妨げます。
79歳からのAI挑戦体験記
最初の一歩
ChatGPTとの出会い:
孫が「これ、すごいよ」と教えてくれました。
最初の反応:
「AIなんて、難しそう」
「パソコンもろくに使えないのに」
「79歳の自分に使いこなせるわけない」
最初の失敗
質問の仕方が分からない:
何を聞けばいいのか
どう書けばいいのか
専門用語が分からない
結果:
思うような答えが返ってこない。
当時の気持ち:
「やっぱり自分には無理だ」
妻の言葉(再び)
「最初から上手くいく人なんていないわよ。
私も一緒に学ぶから、続けてみましょう」
この言葉で、もう一度挑戦する勇気が出ました。
少しずつの進歩
1週間後:
簡単な質問ができるように
1ヶ月後:
AIに健康管理のアドバイスをもらえるように
3ヶ月後:
ブログ記事のアイデアをAIと一緒に考えられるように
今:
このブログを運営し、多くの方と交流
挑戦して得たもの
①新しいスキル
AIの活用方法
②生きがい
ブログでの情報発信
③つながり
読者との交流
④自己肯定感
「79歳でもできた」という自信
⑤希望
「まだまだ成長できる」という実感
失敗を恐れない環境の作り方
家族ができること①:失敗を肯定する
NGな反応:
「ほら、やっぱりできないじゃない」
「だから言ったでしょう」
「無理しなくていいのに」
OKな反応:
「初めてなんだから、当然だよ」
「失敗も経験のうち。次はうまくいくよ」
「挑戦する姿勢が素晴らしい」
家族ができること②:プロセスを褒める
結果ではなく過程を評価:
❌「できたね」(結果のみ)
✅「毎日練習して、すごいね」(努力を評価)
❌「まだできないの?」(否定)
✅「昨日よりうまくなったね」(成長を評価)
家族ができること
③:一緒に学ぶ
伴走者になる:
「教えてあげる」(上から目線)ではなく
「一緒に学ぼう」(対等な関係)
私の場合:
妻が一緒にAIを学んでくれたことが、大きな支えでした。
家族ができること
④:小さな成功を共に喜ぶ
どんなに小さなことでも:
「すごい!できたね!」
「嬉しい!教えて!」
「私もやってみたい!」
喜びを共有することで、次への意欲につながります。
家族ができること
⑤:比較しない
NGな比較:
「〇〇さんはもっとできるのに」
「若い人はすぐできるのに」
「昔のあなたなら」
OKな視点:
過去の本人と比較する
「先週よりできるようになったね」
リハビリ仲間の挑戦例
82歳でスマホを始めた田中さん
きっかけ:
孫とビデオ通話がしたい
最初:
電源の入れ方も分からない
画面を見ても何が何だか
指の操作がうまくいかない
娘さんのサポート:
「お父さん、焦らなくていいよ。一つずつ覚えよう」
3ヶ月後:
孫とビデオ通話
写真を撮って送る
LINEでメッセージ
田中さんの言葉:
「79歳の時は無理だと思っていた。
でも、娘が根気強く教えてくれて、今では
生活に欠かせないものになった」
変化:
表情が明るくなった
孫との会話が増えた
「できた」という自信
他のことにも挑戦する意欲
75歳で絵画を始めた山田さん
きっかけ:
「何か新しいことを始めたい」
周囲の反応:
息子:「今から絵?」(懐疑的)
妻:「やってみたら?」(肯定的)
最初:
思うように描けない
センスがないと落ち込む
「やっぱり無理か」
妻の言葉:
「上手い下手じゃない。楽しむことが大事」
1年後:
地域の展覧会に出品
絵画サークルで友人ができた
毎日の楽しみができた
山田さんの言葉:
「失敗を恐れずに挑戦できたのは、妻が
『失敗してもいい』と言ってくれたから」
「失敗する権利」の重要性
なぜ高齢者に失敗する権利が必要か
①成長の機会
失敗なくして成長なし
②人間としての尊厳
自分で決めて、自分で経験する
③自己肯定感の源
「挑戦した」という事実が価値
④生きる意欲
新しい刺激が脳を活性化
「安全」という名の過保護
家族の心理:
「失敗させたくない」
「傷つけたくない」
「守りたい」
でも、それは:
成長の機会を奪う
人間としての尊厳を奪う
自己決定権を奪う
生きる意欲を奪う
リスクとベネフィットのバランス
過度なリスク回避:
何も挑戦しない = 何も得られない
適度なリスク:
挑戦する = 失敗もあるが、成長もある
私が家族に感謝していること
①信じてくれた
「79歳でも新しいことに挑戦できる」と信じてくれた。
②見守ってくれた
手を出しすぎず、見守ってくれた。
③失敗を責めなかった
うまくいかない時も、「当然だよ」と言ってくれた。
④成長を認めてくれた
小さな進歩を「すごいね」と褒めてくれた。
⑤一緒に喜んでくれた
できた時、一緒に喜んでくれた。
挑戦を続けるコツ
①小さく始める
いきなり大きな目標:
挫折のリスク大
小さな目標:
達成感を積み重ねる
②毎日少しずつ
週末にまとめて:
続かない
毎日10分:
習慣化しやすい
③記録を残す
成長の可視化:
日記
写真
メモ
「こんなにできるようになった」が分かる。
④仲間を見つける
一人で:
孤独、挫折しやすい
仲間と:
励まし合い、継続しやすい
⑤目的を持つ
「なぜ学ぶのか」:
孫と話したい
情報発信したい
社会に貢献したい
目的が、継続の原動力。
まとめ
高齢者の挑戦を支える環境:
失敗を肯定する
プロセスを褒める
一緒に学ぶ
小さな成功を共に喜ぶ
比較しない
見守る(過保護にならない)
失敗する権利の重要性:
成長の機会
人間としての尊厳
自己肯定感の源
生きる意欲
家族へのお願い:
「もう歳なんだから」ではなく
「挑戦する姿勢が素晴らしい」と言ってください。
79歳からのメッセージ:
年齢は挑戦の障害ではありません。
失敗を恐れない環境があれば、何歳からでも
新しいことに挑戦できます。
次回は「認知症予防と自己肯定感」について
お伝えしたいと思っています。
公式サイトはこちらから:https://nayami-kaisyou.net/
公式サイトはこちらから:https://nayami-kaisyou.net/




