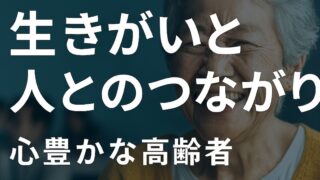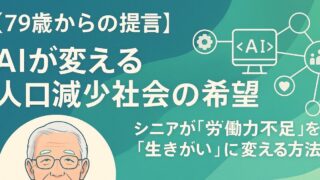2-1. 問題の原因・背景 ― なぜ高齢期に“孤立”が増えるのか
まず現状を押さえます。日本では高齢化が進み、65歳以上の人口割合は2023年に約29.1%に達しています。将来も上昇が見込まれ、2045年には約36%を超える見通しです(総務省・人口推計)。:contentReference[oaicite:1]{index=1}
この背景で重要なのが「単独世帯」の増加です。65歳以上の一人暮らしは男女ともに増加傾向にあり、特に女性の単身率は高くなっています(高齢社会白書)。一人暮らしだと日常的な会話や役割が減りやすく、社会的交流が希薄になりがちです。:contentReference[oaicite:2]{index=2}
さらに、内閣府の全国調査では「孤独・孤立」の実態が明らかになっており、高齢者の一定割合が週に人と会う頻度が少ない、または相談相手がいないと回答しています。長期の孤立は健康リスク(うつ・認知機能低下・死亡リスクの上昇)にもつながるため、早めの手当てが重要です。:contentReference[oaicite:3]{index=3}
2-2. AIを含めた現代のツール事情 ― 高齢者のネット利用はどう変わったか
「ネットは若い人だけのもの」というのはもう古い話です。総務省などの調査によれば、65歳以上のインターネット利用率は年々上昇し、65歳〜69歳では80%を超える層もあります。全体では概ね60%前後の利用率が報告されており(年代差あり)、スマートフォンや簡易なタブレットを使う高齢者も増えています。つまり、AIやオンラインサービスの導入余地は十分にあります。:contentReference[oaicite:4]{index=4}
2-3. 解決策の全体像(3本柱)
ここからは具体策。ポイントは次の3つです。
- 役割づくり(小さな貢献):毎日の生活に「誰かのためにすること」を取り入れる。
- 地域参加(ゆるやかな関係):会う頻度は少なくても安心できる「顔見知り」を作る。
- テクノロジー活用(孤立予防):AIや見守りサービスで物理的距離を補う。
2-4. ステップバイステップ:具体的な実践プラン(番号付き)
- 日々の「役割」を小さく作る
例:近所の共同菜園で水やり当番(月2回)や、自治会の回覧板担当を引き受ける。こうした“負担が小さく続けやすい”役割が自己肯定感を高めます。実際にある町内会の事例では、月1回の当番だけで参加率が上がり、参加者の表情が明るくなったという声があります。 - 「ゆるい集まり」を定期化する
例:図書館や公民館での月1回の読み聞かせ会、散歩会、手芸のサークル。ポイントは強制しないこと。参加は自由で「顔を見せるだけ」でも価値があります。事例では、週1回の散歩グループに参加した高齢者の約6割が孤独感の改善を実感したという報告もあります。 - 家族・近隣と「連絡ルール」を決める
例:毎日夕方に家族と短い電話(1分)をする・週に一度は訪問やビデオ通話を入れる