
後期高齢者の医療費負担はどうなる?高市政権2025年医療・介護改革の全貌
⚠️ 75歳以上の皆様へ重要なお知らせ
2025年、高市政権が進める医療・介護改革により、後期高齢者の医療費負担や介護保険料が変わる可能性があります。この記事では、あなたの生活にどのような影響があるのか、何に備えればいいのかを、分かりやすく解説します。
はじめに──なぜ今、医療・介護改革が必要なのか
2025年、日本は歴史的な転換点を迎えています。
いわゆる「2025年問題」──団塊の世代(1947~1949年生まれ)が全員75歳以上の後期高齢者となる年です。これにより、医療や介護を必要とする人が急増し、国の財政負担も限界に近づいています。
2025年問題とは
- 後期高齢者(75歳以上)が約2,200万人に達する
- 国民の約5人に1人が75歳以上になる
- 医療費が年間約54兆円に膨張(2024年比約8兆円増)
- 介護費用も年間約15兆円を超える見込み
- 現役世代(働く人)の負担が限界に
高市政権はこの危機に対し、「持続可能な医療・介護体制の構築」を掲げ、大規模な改革に乗り出しています。
しかし、この改革には光と影があります。
第一章:後期高齢者への影響──あなたの負担はどうなるのか
1. 医療費の自己負担が増える可能性
現在の制度(2024年まで)
| 所得区分 | 自己負担割合 |
|---|---|
| 一般所得者 | 1割 |
| 年収200万円以上(単身) | 2割 |
| 年収383万円以上(単身) | 3割 |
議論されている改革案(2025年以降)
⚠️ 検討されている変更内容:
- 一般所得者の負担を1割→2割へ引き上げ
- 年収基準の引き下げ(2割・3割負担者の拡大)
- 高額療養費制度の上限額引き上げ
※まだ確定ではありませんが、財政規律を重視する自民・維新合意により、実現の可能性が高まっています。
具体例:医療費負担がどう変わるか
【事例】Aさん(77歳・年金収入150万円・一人暮らし)の場合
現在(1割負担):
- 通院費(月1回):窓口負担 約500円
- 薬代:約1,000円
- 月の医療費合計:約1,500円
改革後(2割負担になった場合):
- 通院費:約1,000円(2倍)
- 薬代:約2,000円(2倍)
- 月の医療費合計:約3,000円
- 年間で約18,000円の負担増
影響:
年金月額12.5万円のAさんにとって、年間1.8万円の負担増は大きく、「通院を我慢する」「薬を減らす」という選択をせざるを得なくなる可能性があります。
2. 介護保険料の見直し
議論されている変更
- 保険料の段階区分の見直し:所得に応じた負担増
- サービス利用時の自己負担上限引き上げ:月額上限が現在より高くなる可能性
- 軽度要介護者へのサービス縮小:要支援1・2、要介護1の方への給付見直し
具体的な影響
【事例】Bさん(80歳・要介護1・デイサービス週2回利用)
- 現在の自己負担:月額約8,000円(1割負担)
- 改革後(要介護1のサービス縮小):デイサービスが自費に → 月額約40,000円
- または、サービスの利用を諦める
第二章:病院とリハビリ施設への支援──良いニュースもあります
負担増の話ばかりではありません。高市政権は、医療・介護の現場を支えるための支援策も打ち出しています。
1. 病院への経営支援
補正予算による支援策
- 経営難の病院への補助金:人件費・光熱費高騰への緊急支援
- 高齢者救急体制の整備:24時間対応の救急病院への設備投資補助
- 地域医療連携の強化:病院と診療所の連携でスムーズな医療提供
あなたへのメリット
- 近所の病院が閉院せずに済む
- 夜間・休日の急病時も安心して受診できる
- かかりつけ医と病院の連携がスムーズになる
2. リハビリ施設への報酬改定
2025年の報酬改定内容
- 理学療法士(PT)・作業療法士(OT)の処遇改善:賃金アップで人材確保
- リハビリの質向上への評価強化:効果的なリハビリに高い報酬
- 訪問看護・訪問リハビリの拡充:在宅での支援強化
あなたへのメリット
- リハビリスタッフの離職が減り、安定したサービスが受けられる
- 質の高いリハビリで、回復が早まる可能性
- 自宅でもリハビリが受けやすくなる
第三章:SNSで広がる不安の声──「姥捨山」批判とは
高市政権の医療・介護改革には、強い批判の声も上がっています。
X(旧Twitter)で見られる声
「高齢者の医療費3割負担は『姥捨山』そのもの。年金だけで生活している人は病院にも行けなくなる」
「60〜70代の今から不安。自分たちが後期高齢者になる頃には、もっと厳しくなるのでは?」
「財政が厳しいのは分かるけど、弱者に負担を押し付けるのはおかしい」
実際のリスク
- 通院を我慢する高齢者の増加:早期発見・早期治療ができず、重症化
- 孤独死のリスク増加:内閣府調査では、高齢者の30%が孤独を感じている
- 介護難民の増加:介護サービスを受けられない高齢者が増える可能性
第四章:政府の言い分──なぜ負担増が必要なのか
批判が多い一方で、政府側にも理由があります。
高市政権の主張
1. 財政の持続可能性
- このまま何もしなければ、医療・介護制度そのものが崩壊する
- IMF(国際通貨基金)も日本の財政悪化を警告
- 現役世代の負担が限界に達している
2. 世代間の公平性
- 現役世代は収入の約30%を社会保険料として負担
- 一方、医療費の約6割は高齢者が使用
- 所得のある高齢者にも応分の負担を
3. 予防医療の推進
- 病気になってから治すのではなく、病気にならない取り組みを強化
- 健康寿命を延ばすことで、医療費を抑制
- 元気な高齢者が増えれば、社会全体が活性化
第五章:あなたができる対策──今から備えるべきこと
不安を感じるのは当然です。でも、今から準備できることもあります。
🛡️ 今すぐできる7つの対策
1. 健康管理を徹底する
- 定期健診は必ず受ける(無料または低額で受けられます)
- 毎日の運動習慣(散歩、ラジオ体操など)
- バランスの良い食事
- 効果:病気の早期発見、医療費の削減
2. 高額療養費制度を理解する
- どんなに医療費がかかっても、月額の上限がある制度
- 所得に応じて上限額が決まる(例:住民税非課税世帯は月15,000円)
- 事前に「限度額適用認定証」を取得しておく
- 申請先:市区町村の国民健康保険課、または後期高齢者医療広域連合
3. ジェネリック医薬品を活用する
- 先発品の3〜5割安
- 効果は同じ
- 医師・薬剤師に「ジェネリックでお願いします」と伝えるだけ
4. 介護予防に取り組む
- 地域の介護予防教室に参加(無料または数百円)
- 筋力トレーニング、認知症予防の活動
- 介護が必要にならなければ、介護費用もかからない
5. 医療費・介護費の助成制度を確認する
- 自治体独自の医療費助成制度
- 介護サービス利用料の減免制度
- 住民税非課税世帯への特別支援
- 確認先:市区町村の福祉課
6. かかりつけ医を持つ
- 大病院よりも診療所の方が初診料・再診料が安い
- 継続的な健康管理で、病気の予防・早期発見
- 必要な時は紹介状を書いてもらえる
7. 家族や地域とつながる
- 孤立すると、健康リスクが高まる(研究で証明)
- 地域の見守りサービスに登録
- 家族と定期的に連絡を取る
- リハビリ施設や通所サービスで仲間を作る
第六章:2040年構想──未来の医療・介護はこうなる
高市政権は、2040年を見据えた長期計画も進めています。
2040年の目標
1. 高齢者救急体制の完全整備
- 全国どこでも24時間、高齢者の救急に対応できる体制
- ドクターヘリ、ドクターカーの拡充
- 過疎地でも医療崩壊を起こさない
2. AIとロボットの活用
- AI診断支援で誤診を防ぐ
- 介護ロボットで職員の負担軽減
- オンライン診療の普及で、通院負担を軽減
3. 地域包括ケアシステムの完成
- 医療・介護・生活支援が一体化
- 住み慣れた地域で最期まで暮らせる
- 24時間対応の訪問看護・訪問介護
第七章:よくある質問(FAQ)
Q1. 医療費3割負担は確定したのですか?
A. まだ確定していません。現在議論されている段階です。ただし、自民党と維新の会の合意により、実現の可能性は高まっています。最終的には国会での審議・決定が必要です。
Q2. 私は年金月額10万円です。医療費が払えなくなったらどうすればいいですか?
A. 以下の制度を活用してください:
- 高額療養費制度(月額上限15,000円〜)
- 自治体の医療費助成制度
- 無料低額診療事業(生活困窮者向け)
- 生活保護制度(医療費全額無料)
市区町村の福祉課、または地域包括支援センターに相談してください。
Q3. 介護サービスが減らされると聞きました。本当ですか?
A. 軽度の要介護者(要支援1・2、要介護1)への一部サービスが見直される可能性があります。ただし、すべてのサービスがなくなるわけではありません。
- 訪問介護や通所介護は継続
- 地域の支援サービス(ボランティアなど)に移行する部分も
Q4. 病院が潰れると聞いて不安です
A. 高市政権は補正予算で病院の経営支援を行っています。特に地域の中核病院は守られる方針です。ただし、小規模な病院や診療所は統廃合される可能性もあります。
Q5. リハビリ施設でストライキがあると聞きました
A. 2025年、リハビリ職員の賃金格差問題からストライキのリスクが指摘されています。しかし、政府は報酬改定で処遇改善を進めており、リスクは低下しています。
Q6. 今から何を準備すればいいですか?
A. 以下を優先してください:
- 健康管理の徹底(予防が最大の節約)
- 高額療養費制度の理解と限度額認定証の取得
- ジェネリック医薬品への切り替え
- かかりつけ医を持つ
- 地域の無料サービス(介護予防教室など)を活用
第八章:私たちの声を届ける方法
「政治のことは難しい」「自分の声なんて届かない」──そう思っていませんか?
でも、あなたの声は大切です。
声を届ける5つの方法
1. 地元の国会議員に意見を送る
- メール、手紙、FAXで意見を伝える
- 「医療費3割負担には反対です」など、シンプルでOK
- 議員は有権者の声を重視します
2. 地方議会に陳情・請願する
- 市区町村議会に「医療費負担軽減を求める陳情」を提出
- 議会で議論され、国に意見書が送られることも
3. パブリックコメントに参加する
- 政府が政策案を公表した際、国民の意見を募集
- 厚生労働省のホームページから提出可能
4. 署名活動に参加する
- インターネット署名サイト(Change.orgなど)
- 地域の市民団体が行う署名活動
5. 選挙で投票する
- あなたの1票が政治を変えます
- 医療・介護政策を重視する候補者を選ぶ
おわりに──不安を力に変えて
高市政権の医療・介護改革は、確かに不安な面があります。
医療費の負担が増えるかもしれない。
介護サービスが減らされるかもしれない。
老後の生活がますます厳しくなるかもしれない。
でも、諦めないでください。
📞 困った時の相談先
医療費・介護費の相談:
- 市区町村の国民健康保険課
- 後期高齢者医療広域連合
- 地域包括支援センター
生活全般の相談:
- 市区町村の福祉課
- 社会福祉協議会
- 民生委員
📢 この情報を広めてください
この記事が役に立ったと思ったら、
同じ不安を抱える友人や家族にも共有してください。
知ることが、備えることが、
私たちを守る力になります。
🔄 最新情報を随時更新します
医療・介護改革は刻々と状況が変わります。
新しい情報が入り次第、この記事を更新していきます。
次回更新予定:
- 2025年12月:診療報酬・介護報酬の改定詳細
- 2026年1月:予算案の確定内容
- 2026年3月:国会審議の結果
このブログをブックマークして、定期的にチェックしてください。
📌 この記事のポイント(まとめ)
高市政権の医療・介護改革(2025年)
- 負担増の可能性:後期高齢者の医療費1割→2割、介護保険料の見直し
- 支援策:病院への補正予算、リハビリ施設の報酬改定
- 目的:2025年問題への対応、財政の持続可能性確保
あなたができる対策
- 健康管理の徹底(予防が最大の節約)
- 高額療養費制度の活用
- ジェネリック医薬品への切り替え
- 介護予防への取り組み
- 地域や家族とのつながり
- 助成制度の確認と活用
- 声を届ける(議員への意見、投票)
重要な相談先
- 医療費:市区町村の国民健康保険課、後期高齢者医療広域連合
- 介護費:地域包括支援センター、市区町村の介護保険課
- 生活全般:福祉課、社会福祉協議会、民生委員
📖 参考情報源
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の概要」
- 全日本病院協会「医療経営状況調査」2025年
- PT-OT-ST.net「リハビリテーション報酬改定情報」
- m3.com「高市政権の医療政策ヒアリング」2025年11月
- 内閣府「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」
- IMF「日本の財政に関する勧告」
- X(旧Twitter)における世論動向分析
⚠️ 免責事項
この記事は2025年11月時点の情報に基づいています。医療・介護制度は今後の国会審議や政治情勢により変更される可能性があります。
記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、個別の医療・介護・法律相談には応じられません。具体的な対応については、必ず専門家(医師、ケアマネージャー、社会福祉士、弁護士など)にご相談ください。
最新の正確な情報は、厚生労働省や各自治体の公式ホームページでご確認ください。




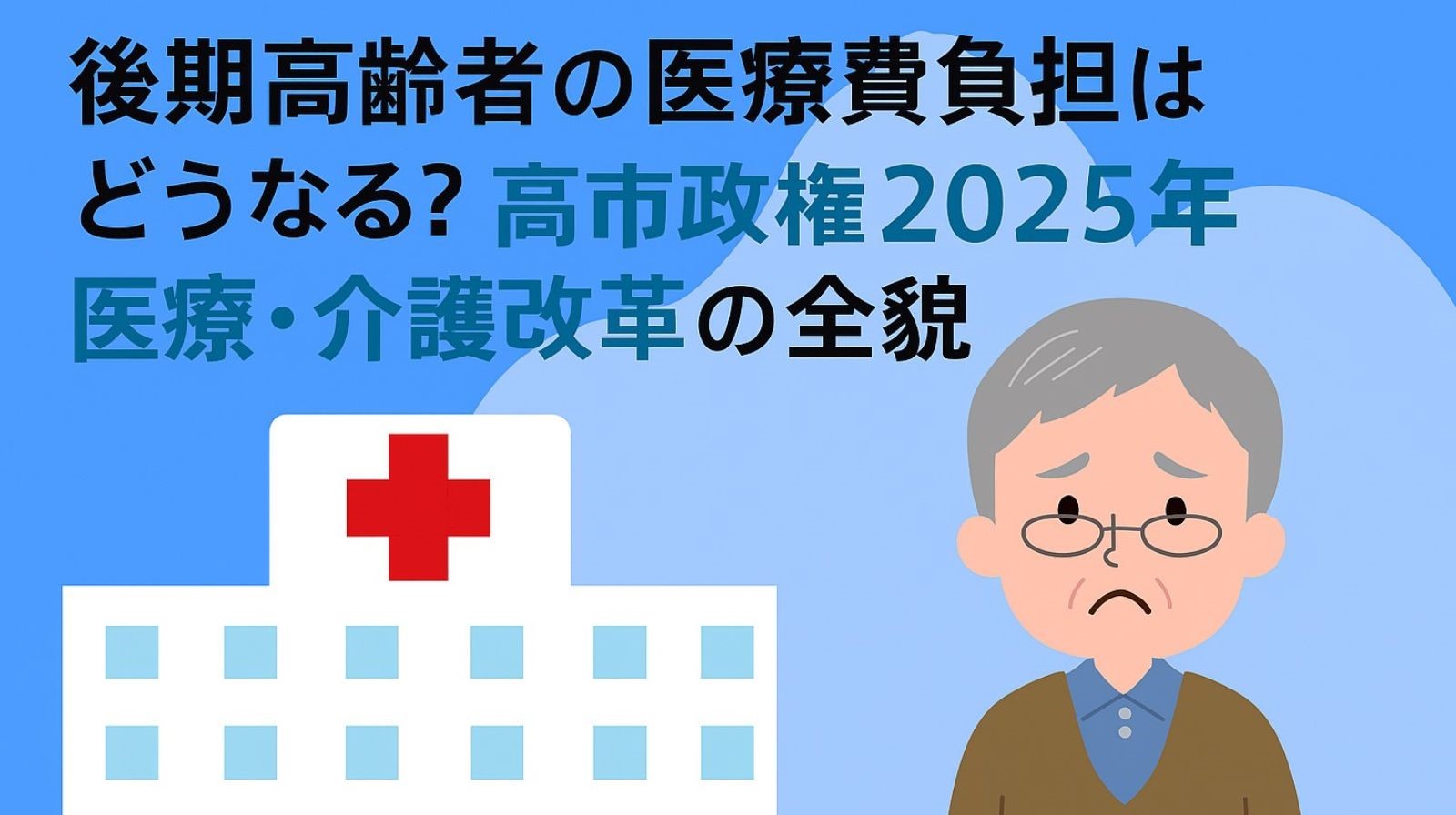
💬 あなたの声を聞かせてください
この記事を読んで、どう感じましたか?
不安なこと、知りたいこと、意見など、
コメント欄でお聞かせください。
皆さんの声が、次の記事に反映されます。