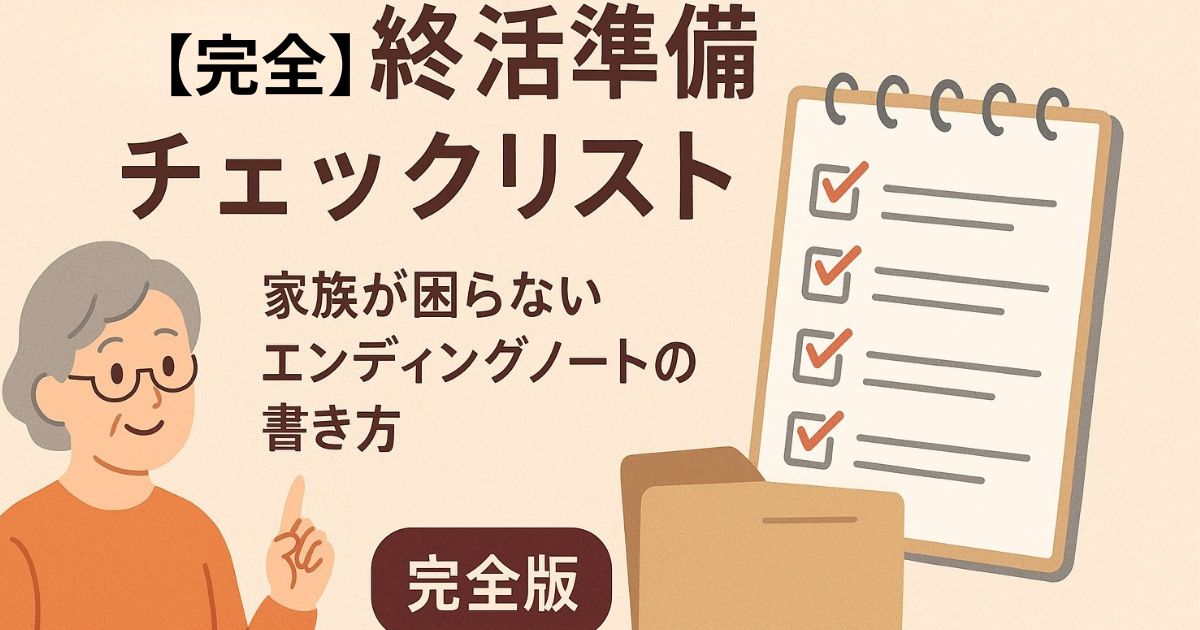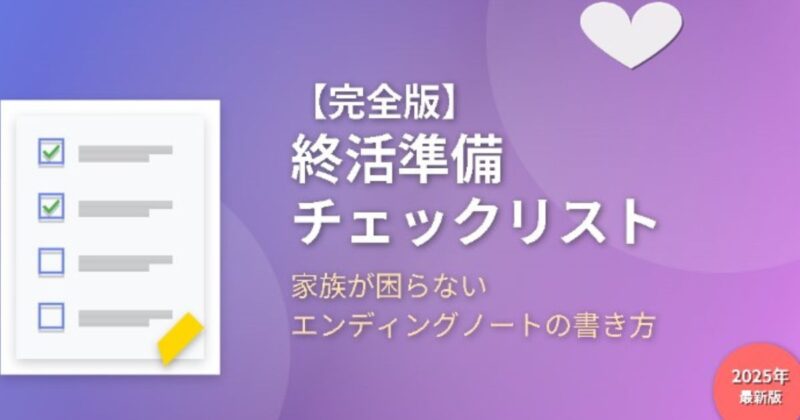
【完全版】終活準備チェックリスト|家族が困らないエンディングノートの書き方
終活とは?なぜ今、必要なのか
終活(しゅうかつ)とは、人生の最期を自分らしく迎えるための準備活動です。2025年現在、60代以上の約65%が「終活に関心がある」と回答していますが、実際に行動している人は30%程度。「まだ早い」と思っている方も多いですが、元気なうちに準備することで、家族の負担を大きく軽減できます。
終活を始めるべき3つの理由
- 家族の負担軽減:葬儀や相続の手続きで家族が迷わない
- 自分の意思を尊重:医療や介護について自分で決められる
- 人生の整理:これまでの人生を振り返り、残りの人生をより豊かに
終活で準備すべき7つの項目
1. エンディングノートの作成
エンディングノートは、自分の希望や大切な情報を記録するノートです。遺言書とは異なり、法的効力はありませんが、家族への大切なメッセージになります。
記載すべき主な内容:
【基本情報】
- 本籍地、マイナンバー
- 運転免許証、パスポート番号
- 健康保険証、年金手帳の保管場所
- 携帯電話の契約情報
【財産関係】
- 預金口座(銀行名、支店名、口座番号)
- 不動産(土地・建物の所在地、権利証の保管場所)
- 株式・投資信託の銘柄
- 生命保険、損害保険の契約内容
- 借入金やローンの有無
- クレジットカード一覧
- 貸金庫の有無と鍵の保管場所
【デジタル情報】
- スマートフォン・パソコンのパスワード
- SNSアカウント(Facebook、Instagram、Xなど)
- メールアカウント
- オンラインバンキングのID・パスワード
- サブスクリプションサービス一覧
- 仮想通貨のウォレット情報
【医療・介護の希望】
- 持病やアレルギー、服薬中の薬
- かかりつけ医、病院名
- 延命治療の希望(する/しない)
- 臓器提供の意思
- 介護が必要になった時の希望(自宅/施設)
- 認知症になった時の財産管理方法
【葬儀・お墓の希望】
- 葬儀の規模(家族葬/一般葬/直葬)
- 宗教・宗派
- 喪主を誰にするか
- 遺影に使いたい写真
- 葬儀で流してほしい音楽
- お墓の有無と場所
- 納骨方法の希望(お墓/納骨堂/散骨/樹木葬)
【家族へのメッセージ】
- これまでの感謝の気持ち
- 大切にしてきた思い出
- 家族へのお願い
- 親しい友人の連絡先
おすすめエンディングノート:
- 「もしもノート」(コクヨ):1,100円、書きやすいシンプル設計
- 「私の歩いた道」:無料、自治体配布も多い
- デジタル版「楽クラライフノート」:アプリで管理、家族と共有可能
2. 遺言書の作成
遺言書は法的効力があり、相続トラブルを防ぐ重要な書類です。
遺言書の種類:
①自筆証書遺言
費用:無料(法務局保管制度利用時は3,900円)
メリット:費用がかからない、一人で作成できる
デメリット:形式不備で無効になる可能性、紛失リスク
作成のポイント:
- 全文を自筆で書く(パソコン不可、財産目録のみパソコン可)
- 日付と氏名を自筆で記入
- 押印(認印でも可、実印推奨)
- 訂正方法が厳格(訂正印と訂正箇所の明示が必要)
2020年から法務局保管制度スタート:法務局に遺言書を預けることで紛失や改ざんを防止。検認手続きも不要に。
②公正証書遺言
費用:5万円〜10万円程度
メリット:公証人が作成するので確実、原本が公証役場に保管され安全
デメリット:費用がかかる、証人2名が必要
こんな人におすすめ:
- 相続財産が多い方
- 相続人が多数いる方
- 複雑な相続を希望する方
- 確実に遺言を残したい方
③秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう方式。あまり利用されていません。
遺言書に書くべき内容:
- 財産の分配方法(誰に何を相続させるか)
- 遺言執行者の指定
- 祭祀継承者の指定(お墓を守る人)
- 付言事項(法的効力はないが、家族へのメッセージ)
3. 財産整理と相続対策
財産目録の作成
すべての財産を一覧表にまとめます。
プラスの財産:
- 預貯金
- 不動産
- 株式・投資信託
- 生命保険
- 自動車
- 貴金属、美術品
マイナスの財産:
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- カードローン
- 未払いの税金
- 連帯保証債務
生前贈与の活用
年間110万円までは贈与税非課税。計画的な生前贈与で相続税対策が可能です。
生前贈与のメリット:
- 相続税の節税
- 財産の使い道を見届けられる
- 家族の喜ぶ顔が見られる
注意点:相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算されます(2024年以降段階的に7年に延長)。
4. デジタル遺品の整理
2025年の大きな課題がデジタル遺品です。
デジタル遺品とは?
- SNSアカウント
- オンラインバンキング
- ネット証券の口座
- スマホやパソコン内のデータ
- クラウドストレージ
- サブスクリプションサービス
- 仮想通貨
- 電子マネー
デジタル遺品整理の手順
- アカウント一覧表作成:サービス名、ID、パスワード、メールアドレスを記録
- デジタル終活アプリの活用:「Digital Keeper」「僕が死んだら」など
- 各サービスの死後対応確認:
- Facebook:追悼アカウントに変更可能
- Google:アカウント無効化管理ツールで設定
- Apple:遺産管理連絡先機能あり
- 削除してほしいデータの指定:見られたくない写真や動画など
- 仮想通貨の秘密鍵管理:家族がアクセスできるよう保管場所を明記
パスワード管理のベストプラクティス
- パスワード管理アプリ(1Password、LastPassなど)を使用
- マスターパスワードのみ紙に記録し、金庫や貸金庫に保管
- 家族に保管場所を伝えておく
5. 身辺整理と断捨離
生前整理は家族の負担を減らすだけでなく、自分の人生を見つめ直す機会にもなります。
整理のステップ
- 思い出の品の選別:残すもの 、処分するものを分類
- 写真の整理:デジタル化してクラウド保存、紙の写真は厳選
- 衣類の整理:1年着ていない服は処分
- 書類の整理:重要書類とそれ以外を分ける
- 家具・家電の処分計画:大型品は業者に依頼
処分方法の選択肢
- リサイクルショップ:まだ使える家具や家電
- フリマアプリ:メルカリ、ヤフオクで売却
- 寄付:NPOや福祉施設へ
- 遺品整理業者:まとめて依頼(費用10万円〜)
- 自治体の粗大ゴミ回収:最も経済的
思い出の品の残し方
- 写真に撮ってデジタル保存
- 家族に分配(事前に希望を聞く)
- エンディングノートに「この品は○○に」と記載
6. 葬儀・お墓の準備
葬儀の種類と費用
①一般葬
費用:150万円〜200万円
参列者:50名以上
特徴:会社関係者や地域の方も参列、告別式あり
②家族葬
費用:80万円〜120万円
参列者:10〜30名程度
特徴:親族と親しい友人のみ、近年最も人気
③一日葬
費用:60万円〜80万円
参列者:少人数
特徴:通夜を省略、告別式のみ
④直葬(火葬式)
費用:20万円〜30万円
参列者:ごく少数
特徴:通夜・告別式なし、火葬のみ、最も経済的
葬儀の事前予約
生前に葬儀社と契約しておくメリット:
- 希望の葬儀内容を詳細に指定できる
- 費用を事前に支払い、家族の負担軽減
- 急な訃報で慌てずに済む
- 割引価格で契約できる場合も
主な葬儀社:
- イオンのお葬式(明瞭価格で人気)
- 小さなお葬式(低価格プラン充実)
- よりそうお葬式
お墓の選択肢
①従来型のお墓
費用:150万円〜300万円(墓石代+永代使用料)
メリット:先祖代々のお墓として継承できる
デメリット:高額、管理が必要、後継者問題
②納骨堂
費用:50万円〜150万円
メリット:室内で天候に左右されない、お参りしやすい
デメリット:一定期間後は合祀される場合も
③樹木葬
費用:30万円〜80万円
メリット:自然に還る、低価格、後継者不要
デメリット:個別参拝できない場合がある
④永代供養墓
費用:10万円〜50万円
メリット:お寺が永代に渡り供養、後継者不要
デメリット:合祀が基本、個別のお参りは期間限定
⑤散骨
費用:5万円〜30万円
メリット:最も低価格、自然に還る
デメリット:お墓参りの場所がない、親族の理解が必要
墓じまいの検討
後継者がいない場合、生前に墓じまいを検討する方も増えています。
墓じまいの手順:
- 親族に相談・同意を得る
- 新しい納骨先を決める
- 現在の墓地管理者に連絡
- 改葬許可申請(自治体)
- 閉眼供養を行う
- 遺骨を取り出し、新しい納骨先へ
- 墓石の撤去・更地化
費用:30万円〜150万円(墓石の大きさによる)
7. 医療・介護の意思表示
リビングウィル(生前の意思表明)
回復の見込みがない終末期医療について、自分の意思を文書化します。
記載すべき内容:
- 延命治療の希望:人工呼吸器、胃ろう、人工透析など
- 心肺蘇生の希望:心臓マッサージ、AED使用について
- 疼痛緩和:痛みを和らげる処置は希望するか
- 臓器提供の意思:提供する/しない、どの臓器か
日本尊厳死協会の「リビングウィル」:医療機関で認知度が高く、入会すると正式な文書を発行してもらえます(年会費2,000円)。
任意後見制度の活用
認知症などで判断能力が低下した時に備え、信頼できる人に財産管理や契約行為を任せる制度。
成年後見制度との違い:
- 任意後見:元気なうちに自分で後見人を選べる
- 法定後見:判断能力低下後、家庭裁判所が後見人を選任
費用:公正証書作成費用約3万円+月額報酬(親族なら無報酬、専門家なら月2〜5万円)
家族と話し合うタイミングと方法
ベストなタイミング
- お盆や正月で家族が集まった時
- 還暦や古希などの節目
- 親しい人の葬儀に参列した後
- 健康診断で大きな問題がなかった時
- ニュースで相続トラブルの話題が出た時
話し合いのコツ
- 重い雰囲気にしない:「元気なうちに整理しておきたくて」と明るく
- 一度にすべて話さない:数回に分けて少しずつ
- 家族の意見も聞く:一方的にならないよう対話形式で
- 書面に残す:口頭だけでなく、エンディングノートに記録
- 定期的に見直す:年1回は内容を確認・更新
話し合うべき具体的な項目
①介護について
- 自宅介護を希望するか、施設入居を考えているか
- 介護費用の準備状況
- 主な介護者は誰か(負担の偏りに注意)
- 介護サービスの利用希望
②医療について
- 延命治療の希望
- 終末期を過ごしたい場所(病院/自宅/ホスピス)
- かかりつけ医の情報共有
③葬儀について
- 葬儀の規模や形式
- 予算
- 喪主は誰か
- 参列者リストの作成
④財産について
- 財産の概要(詳細は遺言書で)
- 相続の基本的な考え方
- 生前贈与の予定
終活で利用できる専門家とサービス
相談できる専門家
①弁護士
相談内容:遺言書作成、相続トラブル対策
費用:相談30分5,000円〜、遺言書作成10万円〜
②司法書士
相談内容:相続登記、遺言書作成支援
費用:相談30分3,000円〜
③行政書士
相談内容:遺言書作成、各種書類作成
費用:相談30分3,000円〜
④税理士
相談内容:相続税対策、財産評価
費用:相談30分5,000円〜
⑤ファイナンシャルプランナー
相談内容:老後資金計画、生前贈与プラン
費用:相談1時間5,000円〜
⑥終活カウンセラー
相談内容:終活全般の相談、エンディングノート記入支援
費用:相談1時間3,000円〜
便利なサービス
①終活セミナー
- 自治体主催(無料)
- 葬儀社主催(無料)
- 専門業者主催(有料、より専門的)
②終活フェア
- 各種サービスを一度に比較できる
- 東京・大阪・名古屋などで定期開催
- 入場無料が多い
③終活コンシェルジュサービス
- 終活全般をサポート
- 月額制または都度払い
- オンライン対応も
終活チェックリスト
□ エンディングノート作成
- □ 基本情報の記入
- □ 財産目録の作成
- □ デジタル情報の整理
- □ 医療・介護の希望記入
- □ 葬儀・お墓の希望記入
- □ 家族へのメッセージ
□ 遺言書作成
- □ 財産の確認と評価
- □ 相続人の確認
- □ 遺言書の種類を選択
- □ 遺言書の作成・保管
□ デジタル遺品整理
- □ アカウント一覧表作成
- □ パスワード管理
- □ サブスクリプション整理
- □ 仮想通貨の管理
□ 身辺整理
- □ 写真の整理
- □ 衣類の整理
- □ 書類の整理
- □ 不用品の処分
□ 葬儀・お墓の準備
- □ 葬儀の形式決定
- □ 葬儀社の比較・選定
- □ お墓の確認・購入
- □ 参列者リスト作成
□ 医療・介護の意思表示
- □ リビングウィル作成
- □ 臓器提供意思表示
- □ 任意後見契約検討
□ 家族との話し合い
- □ エンディングノートの保管場所を伝える
- □ 重要書類の場所を共有
- □ 希望を直接伝える
- □ 定期的な見直しを約束
実際の成功事例
Cさん(68歳・男性)の事例
65歳の時にエンディングノートを作成したCさん。子どもたち3人を集めて自分の希望を伝えました。「最初は縁起でもないと言われたけど、話し合ううちに家族の絆が深まった」とのこと。遺言書も公正証書で作成し、デジタル遺品の整理も完了。「やることをやったから、今は毎日を思い切り楽しめる」と笑顔で話します。
よくある質問(FAQ)
Q1. 終活はいつから始めるべき?
A. 明確な年齢制限はありませんが、60代から始める方が多いです。元気で判断力があるうちに始めるのがベスト。早すぎることはありません。
Q2. エンディングノートと遺言書の違いは?
A. エンディングノートは法的効力がなく、自分の希望や情報を家族に伝えるためのもの。遺言書は法的効力があり、財産の分配方法を指定できます。両方作成するのが理想的です。
Q3. 遺言書は自分で書いても有効?
A. はい、自筆証書遺言として有効です。ただし、形式不備で無効になるリスクがあるため、心配な方は専門家に相談するか、公正証書遺言を選ぶと安心です。
Q4. 家族が終活に反対したら?
A. 「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちを丁寧に説明しましょう。セミナーに一緒に参加したり、テレビ番組を一緒に見たりして、徐々に理解を深めてもらうのが効果的です。
Q5. 一度作った遺言書は変更できる?
A. はい、いつでも変更・撤回できます。新しい遺言書を作成すれば、自動的に古い遺言書は無効になります。人生の変化に合わせて、定期的な見直しをおすすめします。
まとめ
終活は決して縁起の悪いことではありません。むしろ、残りの人生をより充実させ、家族に安心と感謝を残すための大切な準備です。すべてを一度に完璧に行う必要はありません。まずはエンディングノートを1冊購入して、書けるところから少しずつ記入していきましょう。
この5日間の連載を通じて、「AI見守りシステム」「孤独解消のコミュニケーション」「認知症予防」「デジタル健康管理」「終活準備」と、高齢者とその家族が安心して暮らすための知恵をお伝えしてきました。それぞれできることから始めて、より豊かな老後生活を実現してください。
大切なのは、元気なうちに準備すること。そして、家族と対話すること。
あなたとあなたの大切な家族の、安心で幸せな未来を心から願っています。