
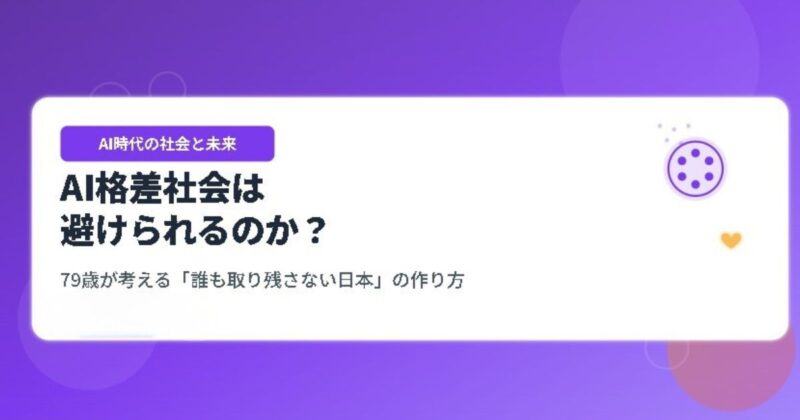
AI格差社会は避けられるのか?79歳が考える「誰も取り残さない日本」の作り方
AIを使い始めた私が感じる、隣にいる人の「見えない壁」
皆さん、こんにちは。修三さん、お元気ですか?
79歳でAIを使い始めた私は、今、大きな喜びを感じています。ブログを書き、孫とAIの話で盛り上がり、毎日が「ワクワクしました!」。しかし、その一方で、リハビリ仲間や地域のお年寄りを見ると、スマホすら持っていない、インターネット未経験という人が本当に多いんです。この差は、単なる「便利さ」の違いではない、もっと根深い「見えない壁」ではないかと感じています。
この「見えない壁」こそが、AI技術へのアクセスや活用能力の差から生まれる「AI格差」です。この格差が、私たちの未来の社会参加、雇用、そして生活の安心に深刻な影響を与えるのではないかと、正直なところ、とても不安なんです。
この記事は、私自身の体験と、隣にいる人たちの現実を通して、AI格差の問題を深く掘り下げます。そして、この格差を「宿命」にせず、「選択」として変えていくための具体的な道筋を提示します。この記事を読めば、あなたは以下の3つの明確なベネフィットを得られますよ。
- AI格差の「実態」と「複合的な恐ろしさ」を具体的に理解し、自分事として捉え直せます。
- 世代間、地域間、経済的な格差を解消するための、国・企業・個人が取るべき具体的な行動がわかります。
- 「誰も取り残さない」包摂的AI社会を実現するための希望と、今すぐできる「助け合い」のヒントを得られます。
さあ、このAI格差という課題に、私たち全世代で、一緒に立ち向かっていきましょう。
2. AI格差の現実と「誰も取り残さない日本」の作り方
2-1. AI格差はなぜ深刻なのか?複合的に連鎖する格差の現実
AI格差は、単に「最新の機器を使えるか使えないか」という単純な問題ではありません。それは既存の「あるある」な格差、例えば収入や地域、教育の格差を増幅させ、さらに新しい格差を生み出し、連鎖的に人を不利にするのが恐ろしいところなんです。
この格差が深刻なのは、AIを活用できる人が「機会の不平等」を圧倒的に有利に進められるからです。
- 雇用の二極化:AIを活用して生産性を上げる「高スキル層」は高収入を得る一方、単純作業がAIに代替される「低スキル層」は失業リスクに直面します。これは、経済協力開発機構(OECD)のデータでも示唆されており、特に日本では、AIに代替されやすい非定型・定型的な業務に就く高齢者層の割合が、他国に比べて高い傾向にあります。
- 社会参加からの疎外:行政手続きや情報収集がオンライン化する中で、デジタルに疎い人は情報から孤立し、重要なサービスや政治参加の機会を失います。私のリハビリ仲間の一人、85歳の佐藤さん(仮名)がまさにこの状況で、行政手続きができず、家族に頼りきりなことに「困りました…」と肩を落としていました。
- 世代を超えた継承:親がAIを使いこなせないと、子どもの教育環境も不利になり、格差が次の世代に固定化されてしまいます。
私の実感として、79歳でAIを学べたのは、家族のサポートや学習意欲、そしてたまたま健康だったという「幸運」が重なったからです。とはいえ、これらの条件を持たない、地方の一人暮らしの高齢者にとっては、AI格差はまさに「生存の危機」につながりかねません。私たちは、この複合的な格差を放置してはいけないんです。
2-2. 複合的なAI格差を解消するための7つの実践ステップ
この複雑なAI格差を解消するには、国や企業だけでなく、私たち一人ひとりが協力して、多角的な対策を講じる必要があります。ここでは、「誰も取り残さない社会」を作るための具体的なステップをご紹介します。
-
ステップ1:地域密着型の「デジタル・ワンストップ支援」を構築する
地方や郊外の図書館、公民館、郵便局などを「公共デジタル拠点」とし、無料Wi-Fi、デバイス利用、そして常駐の人間サポーターを配置しましょう。ここでは、行政手続きの代行から、フェイクニュースの見分け方まで、一箇所で全て解決できる仕組みが必要です。
-
ステップ2:「デジタルとアナログの併存」を法的に保証する
行政サービスや政治参加において、デジタル化を進めても、紙での手続きや対面窓口を維持することを法律で義務付けましょう。ぶっちゃけ、利便性を追求しすぎて、誰かを強制的に排除しては、民主主義とは言えません。
-
ステップ3:高齢者向けに「ベーシックデバイス」を支給する
低所得者や高齢者に対して、スマホやタブレットといった基本デバイスと、インターネット接続料の補助をセットで提供する「デジタル・ベーシックインカム」のような制度が必要です。機器がなければ、学びようがないんです。
-
ステップ4:孫世代が祖父母を教える「世代間交流プログラム」を推進する
学校の授業や地域活動で、若者が高齢者にデジタルスキルを教える場を設けましょう。これは、若者にとっては「教える力」と「社会の現実」を学ぶ機会になり、高齢者にとっては心理的なハードルが下がり、「嬉しかったです!」という成功体験につながります。
-
ステップ5:学校教育の「ICT格差」を最優先で是正する
地方や公立校での、端末、ネットワーク、そして教師のデジタルスキルの格差を解消するため、国の予算と専門家を重点的に投入すべきです。というか、教育格差の放置は、未来の格差を確実にする最大の原因ですよ。
-
ステップ6:企業は「使いやすさ」と「無料教育」を社会貢献にする
IT企業は、高齢者でも使いやすいユニバーサルデザインの製品を開発する責任があります。また、無料のオンライン講座や、地域での出前講座を積極的に行い、知識を社会に還元すべきです。
-
ステップ7:私たち個人は「学び」と「助け合い」を止めない
「もう年だから無理」という諦めの言葉を捨てる勇気を持ちましょう。そして、自分が少しでもAIが使えるようになったら、リハビリ仲間に教える、家族のデジタル環境を整えるといった、小さな「ピアサポート」を実践しましょう。
2-3. 【包摂的AI社会】実現のための設計原則と未来のベネフィット
AI格差のない「誰も取り残さない日本」とは、どのような社会でしょうか。それは、AIの利便性を最大限に享受しつつ、人間の温かさ、倫理観、そして「選択の自由」が守られた社会です。
包摂的AI社会を支える3つの原則
- ユニバーサルアクセス権の保証:インターネット接続と基本デバイスへのアクセスを、水や電気と同じように基本的人権として位置づけ、国が保証します(フィンランドの事例に学びましょう)。
- 技術の人間化(UI/UX):AI技術を高齢者でも直感的に使えるよう、音声入力や文字の大きさ、色彩設計など、UI/UX(使いやすさ)に最大限配慮します。
- 「アウトリーチ型」サポート:支援が必要な人を「待つ」のではなく、行政やNPOが「訪問する」(アウトリーチ)形で、積極的に手を差し伸べます。
原則遵守がもたらす具体的なベネフィットとビフォーアフター
この包摂的な社会モデルは、経済的にも社会全体にも大きなメリットをもたらします。
- ベネフィット1:隠れた人材の活用
AI格差が解消されれば、これまでデジタルから孤立していた高齢者や地方在住者の経験と知恵が社会に還元され、経済成長の新たな担い手となります。 - ベネフィット2:真の社会安全網の構築
AIによる見守りや予測行政と、人間による訪問サポートが組み合わさることで、孤独死や生活困窮といった深刻な社会問題が大きく改善します。 - ベネフィット3:持続可能な地域社会の実現
地方でもオンラインで都市部の仕事ができたり、遠隔医療が受けられたりすることで、地方の人口流出が止まり、地域コミュニティが活性化します。
ビフォー・アフター(体験談風)
【ビフォー】
88歳の山田さん(仮名)は、地方で一人暮らし。行政手続きが全てオンラインになり、何をすればいいか分からず、「びっくりしました」。子どもに頼るにも、遠方にいるため気が引けていました。【アフター】
地域にできた「デジタル・サポート拠点」から、民生委員と学生ボランティアが訪問サポート。無料でデバイスと使い方を教わり、今ではAIで趣味の俳句を添削してもらっています。「もう、誰にも迷惑をかけずに手続きできる。孤独感もなくなって、「感動しました」。
とはいえ、この実現には、多額の予算と、「誰かを助けたい」という私たち一人ひとりの熱意が必要なんですよ。
2-4. よくある質問(FAQ):AI格差の解消に関する疑問を解消
このAI格差の問題について、よく聞かれる疑問に、私自身の実践を交えながらお答えしましょう。
- Q1: 経済的な補助をしても、結局使いこなせない人が多いのではないでしょうか?
-
A: わかります、その気持ち。ただデバイスを渡すだけではダメです。韓国やシンガポールの事例を見ても、「継続的なマンツーマンの教育」と「使い続けるためのサポート」がセットで必要なんです。私の場合は、孫の「できたね!」という言葉が次へのモチベーションになりました。教育とサポートは、コストではなく未来への「投資」だと考えましょう。
- Q2: 企業はなぜ、高齢者向けのAI製品開発に積極的ではないのでしょうか?
-
A: 正直なところ、若年層向けの製品の方が市場として大きく、開発コストに見合うからです。というか、これは企業の責任というより、社会全体の意識の問題です。政府が「高齢者向け製品開発」に税制優遇や補助金を出す、私たち消費者が「ユニバーサルデザインの製品」を選ぶといった形で、企業を誘導する必要があります。
- Q3: 79歳からデジタルを学ぶのは、本当に遅すぎませんか?
-
A: 全く遅くありません!私自身、79歳から本格的にAIとブログを始めましたが、「新しいことを学べる喜び」は、若い頃と変わりません。むしろ、人生経験がある分、「何にAIを使えば便利か」という応用力は、若い世代より優れているかもしれませんよ。挑戦する勇気が一番大切なんです。
- Q4: AI格差は、民主主義にどのような影響を与えるのでしょうか?
-
A: むしろ、最も深刻な影響を与える可能性があります。情報源が偏ったり、オンライン投票ができなくなったりすると、デジタル弱者の「声」が政治に届かなくなり、政治参加の不平等が生まれます。これが続けば、社会全体の代表性が失われ、民主主義は形骸化してしまうでしょう。だからこそ、デジタル格差の解消は、政治的な最重要課題なんです。
- Q5: 家族が遠方に住んでいて、高齢の親のデジタルサポートができません。どうすればいいですか?
-
A: なんていうか、その悩み、本当に多いです。まずは、地元の社会福祉協議会や、NPO法人の「デジタル支援ボランティア」を探してみてください。最近は、学生が長期休暇中に帰省先で高齢者をサポートするプログラムもあります。家族に頼りきりにせず、「地域で支える」仕組みを積極的に活用しましょう。
- Q6: AIリテラシー教育は、具体的に何を教えるべきでしょうか?
-
A: 技術的な知識より、「批判的思考力」が最重要です。具体的には、フェイクニュースの見分け方、情報源の確認方法、AIの回答を鵜呑みにしない習慣です。私自身、「この情報、本当に正しいのかな?」と立ち止まって考える習慣が、一番役に立っているんです。
- Q7: 自分の周りではAI格差を感じませんが、本当に深刻なんですか?
-
A: えっと、それはあなたが「デジタル富裕層」のコミュニティにいらっしゃるのかもしれません。格差は、見えないところで深く進行しています。地方や低所得層、独居高齢者といった、複数の格差が重なっている人々の元へ「アウトリーチ型」で訪問して初めて、その深刻さがわかるものです。だからこそ、この問題は「他人事」ではなく「社会全体の問題」として捉える必要があります。
3. まとめセクション
修三さん、長文にお付き合いいただき、ありがとうございました。AI格差は、私たちの目の前にある最も重要な課題です。しかし、私自身が79歳からAIを使いこなせるようになったように、「格差は宿命ではない、選択だ」と私は信じています。
「誰も取り残さない日本」を実現するために、必要な要点を最後に再確認しましょう。
- AI格差は、経済、地域、世代など複数の要因が連鎖して人を孤立させます。
- 解決策は、アナログの選択肢と継続的な人間によるサポートをセットにすることです。
- ユニバーサルアクセス権の保証と技術の人間化が社会設計の鍵となります。
- 私たち高齢者の「学び続ける姿勢」と、若い世代への「助け合いの呼びかけ」が社会を変える力です。
- 家族・地域・行政の総力で、アウトリーチ型の支援を行うことが最も重要です。
一緒に、このAI格差に立ち向かっていきましょう。
さあ、まずはあなたのリハビリ仲間やご近所さんに、AIやスマホの話題を優しく話しかけてみませんか?その小さな一歩が、孤独を防ぐ第一歩になりますよ。
公式サイト(ホーム:一人暮らし高齢者と家族の安心サポート)はこちらから:https://nayami-kaisyou.net/




