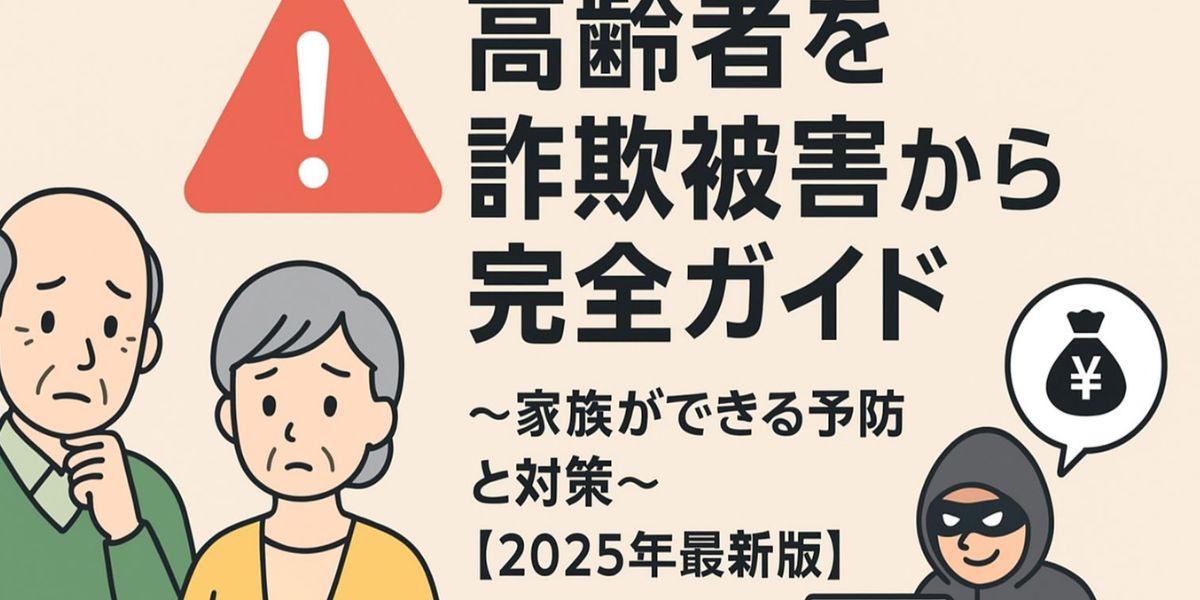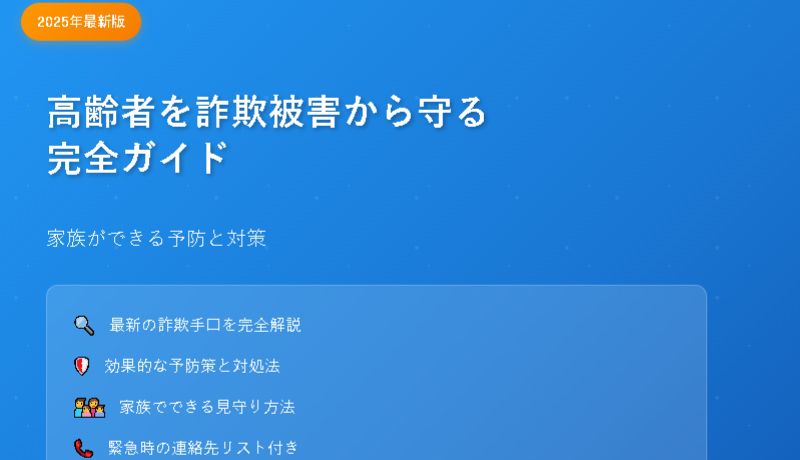
高齢者を狙った詐欺被害は年々巧妙化し、被害額も増加の一途を辿っています。
警察庁の統計によると、特殊詐欺の被害者の約7割が65歳以上の
高齢者となっており、家族による予防と対策が急務となっています。
「うちの親は大丈夫」「詐欺なんて見抜けるはず」
そう思っていませんか?
実は、知的レベルや社会経験に関係なく、誰もが
詐欺の被害者になる可能性があります。
特に一人暮らしの高齢者は、孤独感や不安感につけ込まれやすく、
注意が必要です。
この記事では、高齢者を詐欺被害から守るために家族ができる
具体的な予防策と、万が一の際の対処法について詳しく解説します。
高齢者が狙われる理由とは?詐欺師の心理を知る
なぜ高齢者が標的になるのか
詐欺師が高齢者を狙う理由は複数あります。
まず、貯蓄額が比較的多いことが挙げられます。
退職金や年金、不動産売却益など、まとまった資産を
持っている可能性が高いためです。
また、情報収集手段が限られていることも要因の一つです。
インターネットやSNSに慣れ親しんでいない高齢者は、
最新の詐欺手口に関する情報を得にくく、古い常識で
判断してしまいがちです。
心理的な隙を突く手口
詐欺師は高齢者の心理状態を巧みに利用します。
「家族に迷惑をかけたくない」という気持ちや、
「誰かの役に立ちたい」という善意、「損をしたくない」
という不安などを煽り、冷静な判断力を奪います。
特に一人暮らしの高齢者は、普段人と話す機会が少ないため、
詐欺師との会話を「久しぶりの人との交流」として
受け入れてしまうケースもあります。
2025年最新!高齢者を狙う詐欺の種類と手口
オレオレ詐欺・親族詐欺
手口の特徴
息子や孫を名乗り、「事故を起こした」「会社のお金を使い込んだ」
などと緊急事態を装い、すぐにお金が必要だと訴えかける手口です。
最新の傾向
近年では、コロナ禍を利用した「PCR検査で陽性が出た」
「隔離されているから代わりの人がお金を受け取りに行く」
といった新しいパターンも登場しています。
架空請求詐欺
手口の特徴
「未払いの料金がある」「法的措置を取る」などと脅し、
架空の料金を請求する手口です。
ハガキ、メール、SMSなど様々な手段で接触してきます。
見分け方のポイント
正当な請求であれば、具体的なサービス名や
利用日時が明記されているはずです。
曖昧な表現や「本日中に連絡」などの緊急性を
煽る文言は詐欺の可能性が高いです。
還付金詐欺
手口の特徴
市役所や税務署の職員を名乗り、「医療費の還付金がある」
「税金を払いすぎている」として、ATMでの操作を促す手口です。
ATM操作の危険性
「ATMで還付金を受け取る」ことは絶対にありません。
ATMでは振り込みしかできないため、操作をすれば
確実に詐欺師の口座にお金が送金されてしまいます。
投資詐欺・金融商品詐欺
手口の特徴
「必ず儲かる投資話がある」「今だけの特別な金融商品」として、
根拠のない高利回りを謳って投資を勧誘する手口です。
見分け方
金融商品取引法により、「必ず儲かる」「元本保証」などの
断定的な表現は禁止されています。
このような勧誘を受けた場合は詐欺を疑いましょう。
家族ができる予防策~日常的なコミュニケーションが鍵
定期的な連絡体制を確立する
毎日の安否確認
可能な限り毎日、短時間でも親と連絡を取る習慣をつけましょう。
LINEやメール、電話など、親が使いやすい手段を選ぶことが大切です。
「合言葉」を決めておく
オレオレ詐欺対策として、家族間で「合言葉」を
決めておくことをおすすめします。
お金の話が出た際は、必ず合言葉を確認するルールにしておけば、
詐欺を見抜きやすくなります。
詐欺に関する情報共有
最新手口の情報提供
警察署や自治体が発行する詐欺防止チラシを定期的に親に渡したり、
ニュースで報じられた新しい手口について話し合ったりしましょう。
「相談しやすい雰囲気」作り
「騙された」と打ち明けることは、高齢者にとって非常に恥ずかしく、
自尊心が傷つくことです。
普段から「判断に迷ったら必ず相談して」という
雰囲気を作っておくことが重要です。
環境整備による予防
留守番電話の活用
知らない番号からの電話には出ないよう、
留守番電話を活用することを勧めましょう。
本当に必要な電話であれば、メッセージを残すはずです。
訪問販売お断りステッカー
玄関に「訪問販売お断り」「セールスお断り」のステッカーを
貼ることで、悪質な業者の訪問を減らすことができます。
被害を未然に防ぐ!家族が教える見分け方のポイント
電話詐欺の見分け方
声の確認方法
息子や孫を名乗る電話があった際は、必ず「風邪を引いている」
「携帯電話を変えた」などの理由で声が違うことを説明してきます。
このような場合は、一度電話を切って、知っている番号に
かけ直すよう親に教えておきましょう。
緊急性への対処
「今すぐ」「今日中に」などの緊急性を煽る言葉が出たら、
一旦冷静になることが重要です。本当の緊急事態であれば、
必ず他の家族にも連絡があるはずです。
書面による詐欺の見分け方
送信者情報の確認
正当な請求書や公的機関からの通知には、必ず正確な住所、
電話番号、担当者名が記載されています。
これらが曖昧だったり、携帯電話番号だけの
場合は詐欺の可能性が高いです。
文面の特徴
詐欺の文面には「至急」「緊急」「法的措置」「差し押さえ」
などの脅し文句が多用されます。
また、日本語が不自然だったり、誤字脱字がある場合も要注意です。
万が一被害に遭った場合の対処法
被害発覚後の初動対応
証拠の保全
詐欺の証拠となる電話の録音、メール、書面などは絶対に
捨てずに保管しておきましょう。
警察への届け出や、銀行での振り込み停止手続きに必要になります。
金融機関への連絡
振り込み詐欺の場合、被害発覚後すぐに振り込み先の
金融機関に連絡することで、口座凍結により被害金の
回収が可能な場合があります。
警察・相談機関への届け出
警察への被害届
最寄りの警察署で被害届を提出しましょう。
同様の手口による被害を防ぐためにも、恥ずかしがらずに
届け出ることが重要です。
消費生活センターへの相談
消費者ホットライン(188)では、詐欺被害の
相談を無料で受け付けています。
被害回復のアドバイスや、今後の対策について
専門家から助言を受けることができます。
地域と連携した防犯対策
地域包括支援センターとの連携
見守りネットワークの活用
地域包括支援センターでは、高齢者の
見守りネットワークを構築しています。
一人暮らしの親がいる場合は、このサービスを活用することで、
詐欺被害の早期発見につながります。
防犯教室への参加
多くの自治体で、高齢者向けの防犯教室を開催しています。
親に参加を勧めることで、最新の詐欺手口について学ぶことができます。
近所との情報共有
町内会・自治会での情報交換
近所で詐欺の予兆(不審な電話や訪問者)があった場合は、
町内会や自治会を通じて情報共有することで、地域全体での
防犯意識を高めることができます。
最新技術を活用した詐欺対策
迷惑電話対策機器の導入
自動録音機能付き電話
通話を自動録音する機能付きの電話機を使用することで、
詐欺師が電話をかけにくくなります。
また、録音があることで、後から詐欺の証拠として活用できます。
迷惑電話チェッカー
発信者番号から迷惑電話の可能性を判定し、警告表示する機器もあります。
技術的なサポートが必要な場合は、家族が設定を手伝いましょう。
スマートフォンアプリの活用
家族見守りアプリ
位置情報共有や定期的な安否確認ができるアプリを活用することで、
親の安全を遠隔からも確認できます。
まとめ:家族の絆が最大の防犯対策
高齢者の詐欺被害を防ぐためには、家族の継続的な関わりと、
日常的なコミュニケーションが最も重要です。
完璧な防犯対策というものは存在しませんが、以下のポイントを
実践することで、被害のリスクを大幅に減らすことができます。
今日からできる3つのアクション
1. 定期的な連絡:毎日短時間でも親と話す時間を作る
2. 情報共有:最新の詐欺手口について親と一緒に学ぶ
3. 相談しやすい環境作り:「困ったときは必ず家族に相談」を約束する
詐欺師の手口は日々巧妙化していますが、家族の愛情と絆があれば、
どんな詐欺からも大切な親を守ることができます。
一人で抱え込まず、家族全体、そして地域全体で高齢者を見守っていきましょう。
何よりも大切なのは、「被害に遭っても、家族は絶対に責めない」という
安心感を親に提供することです。
その安心感こそが、詐欺に立ち向かう最大の武器となるのです。
緊急連絡先一覧
– 警察:110番(緊急時)、#9110(相談専用)
– 消費者ホットライン:188
– 振り込め詐欺救済法に基づく公告サイト:
[一般社団法人全国銀行協会](https://www.zenginkyo.or.jp/)
参考情報
– [警察庁:特殊詐欺対策](https://www.npa.go.jp/)
– [国民生活センター:高齢者の消費者トラブル](https://www.kokusen.go.jp/)
– [金融庁:金融サービス利用者相談室](https://www.fsa.go.jp/)