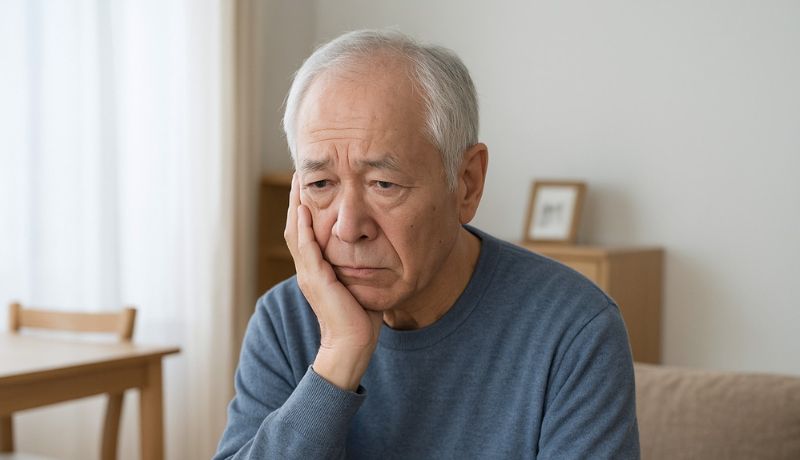
[the_ad id=”583″]
高齢者一人暮らし!対策・対処法は!?
高齢者の一人暮らしは、近年増加傾向にあり、2021年には65歳以上の
高齢者世帯の約28.8%が一人暮らしとなっています。
一人暮らしを選ぶ理由としては、経済的な理由や、子供に負担を
かけたくない、自立した生活を送りたいといった理由が挙げられます。
しかし、一人暮らしには、孤独感や健康面でのリスク、
経済的な問題など、様々な課題も伴います。
高齢者孤独感
高齢者の孤独感は、社会問題の一つとして認識されています。
一人暮らしの増加や、友人・知人との交流の減少、健康面や経済面での
不安などが孤独感を引き起こす要因として挙げられます。
孤独感は、健康状態の悪化や認知症のリスクを高める可能性も
指摘されており、適切な対策を講じることが重要です。
後期高齢者向きの利用しやすい制度
後期高齢者(原則75歳以上)を対象とした政策には、医療、介護、
生活支援など、さまざまな分野があります。
主な政策やサービスには、以下のようなものが挙げられます。
医療制度:
後期高齢者医療制度は、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)が
加入する独立した医療制度です。
医療費の自己負担割合は所得に応じて1割、2割、または3割となります。
介護保険制度:
介護が必要な状態になった場合に利用できる居宅サービス、
施設サービス、地域密着型サービスなどがあります。
介護予防や日常生活支援を目的としたサービスも提供されています。
生活支援・見守り:
配食サービス: 自治体によっては、お弁当の宅配サービスを
通じて高齢者の安否確認を行う事業があります。
緊急通報システム: 緊急時にボタン一つで通報できる装置の貸し出しや、
24時間見守りサービスを提供している自治体もあります。
住宅改修の助成:
日常生活の便宜を図るための住宅改修費用の一部を助成する
事業を行っている自治体もあります。
社会参加・生きがい:
就業支援: 高齢者が働き続けられるよう、定年の引き上げや
継続雇用制度の導入が推進されています。
学習機会の提供: 高齢者の学習意欲に応え、生きがいのある
充実した生活を支援するための学習機会が提供されています。
地域活動の促進: 高齢者の自主的な組織である老人クラブの
活動支援や、世代間の交流を促進する事業も行われています。
高齢者の一人暮らしの親族に居ると、安否が何時も心配です。
電話を数回かけても応答が無ければ、バスに乗って見に行く回数が増えてきました。
新聞販売店にそのままの日が2日ほど続けば、連絡して下さいとお願いしたりしています。
高齢者になると、賃貸住宅の入居も難しくなります、問題点が山済みだと思っています。
高齢者の一人暮らしは、ご家族にとって安否確認の面で大きな心配事となりますね。
お電話をかけても繋がらない時に、実際に足を運んで安否を
確かめるというお気持ち、とてもよく分かります。
新聞販売店にお願いしているというお話からも、ご家族の深い愛情と、
それだけ安否確認に苦慮されている状況が伝わってきます。
高齢者の一人暮らしが抱える問題は多岐にわたりますが、中でもご家族が最も
心配される安否確認の問題、そして高齢者自身の住まいに関する問題は、
近年特に深刻化しています。
これらの問題意識について、以下にまとめました。
高齢者の安否確認における問題点
1. 物理的な距離と時間的制約
遠方に住んでいる場合、電話での連絡が主となりますが、数回の不通で
「何かあったのでは」という不安に駆られ、遠方まで駆けつけることになります。
しかし、物理的な距離やご自身の仕事・生活の都合もあり、
毎回すぐに駆けつけることは難しいのが現状です。
2. 安否確認の手段の限界
電話やメール、SNSなどは便利なツールですが、高齢者が常に
携帯しているとは限りません。
また、体調不良で電話に出られない、スマートフォンの操作が難しいと
いった状況も考えられます。
新聞販売店に協力を求める方法は有効ですが、あくまで補助的なものであり、
緊急時の即座の対応には限界があります。
3. 孤独死のリスク
安否確認が遅れた結果、孤独死に至るケースも後を絶ちません。
孤独死は、発見の遅れが精神的にも社会的にも大きな影響を及ぼし、
ご家族にとって深い悲しみと後悔を残します。
こうしたリスクをいかに軽減するかが、最大の課題となっています。
高齢者の住まいにおける問題点
1. 賃貸住宅への入居が困難
高齢者は、家賃の滞納や孤独死のリスクを懸念され、
賃貸住宅の審査に通りにくいのが現状です。
連帯保証人を求められても、身近な親族に頼るのが難しかったり、保証会社との
契約が必要になったりと、入居へのハードルは非常に高いです。
2. 住宅のバリアフリー問題
高齢になると、自宅内の段差や滑りやすい床が転倒事故の原因となります。
しかし、住宅改修には費用がかかり、経済的な問題から
踏み切れないケースも多いです。
また、賃貸住宅の場合は、オーナーの許可が必要となり、
自由な改修は難しいという問題もあります。
まとめ:多角的なアプローチの必要性
高齢者の一人暮らしにおけるこれらの問題は、単にご家族だけの
努力で解決できるものではありません。
公的な制度や民間サービス、そして地域社会の連携が不可欠です。
例えば、緊急通報システムや配食サービスは、安否確認を自動化・日常化する上で
有効な手段となります。また、
高齢者向けの賃貸住宅やサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、
高齢者の住まいの選択肢も増えてきています。
ご家族が抱える不安は尽きませんが、まずは一人で悩まずに、お住まいの
地域の地域包括支援センターに相談してみることをお勧めします。
専門家が様々な公的サービスや民間の見守りサービスを紹介し、
具体的な解決策を一緒に考えてくれます。
高齢者が安心して暮らせる社会の実現は、社会全体の大きな課題です。
ご家族が抱える不安を軽減するためにも、高齢者自身が生き生きと
暮らせるための環境づくりが求められています。
[the_ad id=”5982″]




